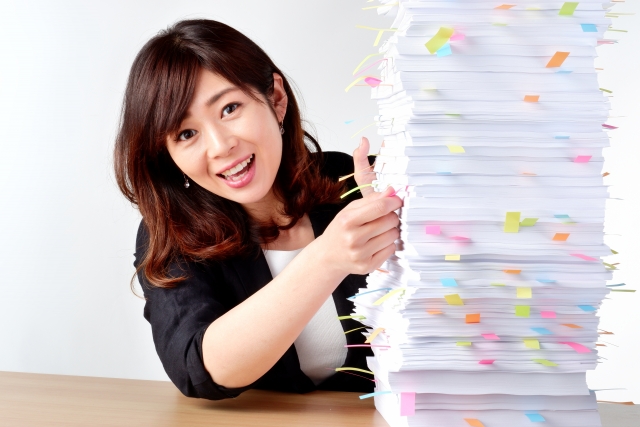
事実婚にまつわる書類【まとめ】
2020-01-24
事実婚とは、婚姻届を提出していないため法律上は夫婦とは認められないものの、実態としては男女が夫婦として生活している状態のことをいいます。
何ら手続をしなくても事実婚は成立しますが、そのままでは法律上の夫婦なら受けられる特典が受けられなかったり、2人の関係も不安定になりがちというデメリットもあります。
このようなデメリットを避けるため、事実婚の夫婦であってもさまざまな書類を作成・提出して手続きを行うことが推奨されます。
この記事では、事実婚として生活していく夫婦が知っておきたいさまざまな書類についてまとめてみます。
事実婚であることを証明するための書類
法律上の夫婦であれば、婚姻届を提出することによって戸籍や住民票に「夫」「妻」と記載されるため、夫婦であることを証明することは容易です。しかし、事実婚の夫婦については事実婚の状態に入ることによって自動的には夫婦であることを証明する書類は作成されません。
結婚という形に縛られず、面倒な手続がいらないことは事実婚のメリットでもあります。しかし、事実婚であることを証明できれば単なる同棲カップルでは受けられないさまざまな法律上の利益を受けることができます。
事実婚であることを証明するための書類としては、以下のようなものがあります。
住民票
同棲カップルの場合は、住民票の続柄の欄に「同居人」と記載されます。
事実婚の夫婦として同居するときには、役所に「住民異動届」を提出する際、続柄の欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記入しましょう。役所によって取扱いが異なることがあるようですので、念のため窓口の係員にも事実婚であることを告げるといいでしょう。
事実婚契約書
婚姻届に代わるものとして「事実婚契約書」を交わしておくのがおすすめです。
事実婚契約書は様式や記載内容に決まりはありませんが、一般的には以下のような内容を盛り込みます。
・日常生活における決まりごと
・生活費の分担
・子どもの親権や教育方針
・貞操を守ること
・関係を解消する際の慰謝料や財産分与
事実婚契約書は公正証書にしておくと証明力が高くなるので、さまざまな手続をスムーズにできるようになります。
パートナーシップ証明書
一部の自治体では、二人の関係性を自治体の長に宣誓することで、夫婦が受けられるさまざまな行政サービスが事実婚の夫婦でも受けられるようになる「パートナーシップ制度」という制度が実施されています。
この宣誓をすると、「パートナーシップ証明書」や「パートナーシップ宣誓書受領証」という証明書が交付されます。この書類によって事実婚であることを証明することができます。
パートナーシップ制度を導入している自治体はまだ多くありませんが、全国の自治体で順次導入が進んでいます。
事実婚を証明することで受けられるサービス
法律上の夫婦と同一とまではいきませんが、事実婚であることを証明できれば以下のようなさまざまな公的サービスや企業のサービスを受けることができます。
いずれのサービスを受ける場合にも上記の3つの書類のうち最低1つは必要になるので、準備しておいた方がいいでしょう。
・国民年金の第3号被保険者
・健康保険の被扶養者
・不妊治療費助成金の受給
以下のものについては企業ごとに取扱いが異なりますが、手続する際には事実婚であることを証明する書類が必要になります。
・勤務先から家族手当の支給を受けること
・生命保険の受取人になること
・手術への同意や病状説明を受けること
・クレジットカードの家族会員になること
・携帯電話(スマホ)料金の家族割引
・自動車保険料の家族割引
事実婚では相続権がないため遺言書が重要
事実婚の配偶者には相続権がありません。そのため、財産を承継するためには生前贈与をしておくか、遺言書を作成して遺贈することが必要です。
子どもができるとさまざまな書類が必要になることも
事実婚の夫婦に子どもが生まれたとき、出生届を提出するだけでは父と子は法律上の親子として認められません。そのため、2人で子どもを育てていくためにさまざまな書類が必要になる場合があります。
認知届
父と子の間に法律上の親子関係を発生させるためには、認知をする必要があります。認知するためには、父が役所に「認知届」を提出します。
親権者の変更申立書
認知しただけでは、子どもの親権者は母のままです。子どもに関する公的な手続はすべて母が法定代理人として行う必要があります。父母の合意だけで親権者を変更することはできません。
親権者を父に変更するためには、「親権者の変更申立書」を家庭裁判所に提出して調停・審判を経て許可を受ける必要があります。
子の氏の変更許可申立書
子どもが生まれて出生届を提出すると、子どもは母の戸籍に入って母の姓になります。父が子を認知しても変更されません。
子の姓を父の姓に変更する場合は、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出して許可を受けなければなりません。
関係を解消するときは離婚協議書を作成しよう
事実婚を解消するときは、法律上の夫婦が離婚する場合と同様に財産分与や慰謝料、養育費の請求が認められます。これらの事項を取り決める場合は口約束だけでなく、離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書の証明力を高め、約束を確実に守ってもらうためには公正証書で作成するのがおすすめです。
事実婚夫婦の一方が亡くなったとき
事実婚夫婦の一方が亡くなったとき、生存している方に相続権はありませんが、遺族年金の受け取りと、亡くなった方が賃借していた自宅に住み続けることは可能な場合があります。
ただし、どちらの場合も事実婚であったことを証明しなければなりません。冒頭でご紹介した証明書類のうち最低いずれか1つは必要になります。
まとめ
形式にとらわれない事実婚であっても、生活していくうえではさまざまな書類が必要になります。そのなかでも最も基本となるのは、事実婚であることを証明する書類です。
「事実婚証明書」は、いざ作成しようと思っても何を書けばいいのか分からない方も多いでしょうし、記載内容によっては関係を解消する際などに不利になってしまうおそれもあります。
安心して事実婚として夫婦生活を送っていくためには、早いうちに夫婦の問題に詳しい弁護士に相談しておくのがいいでしょう。
