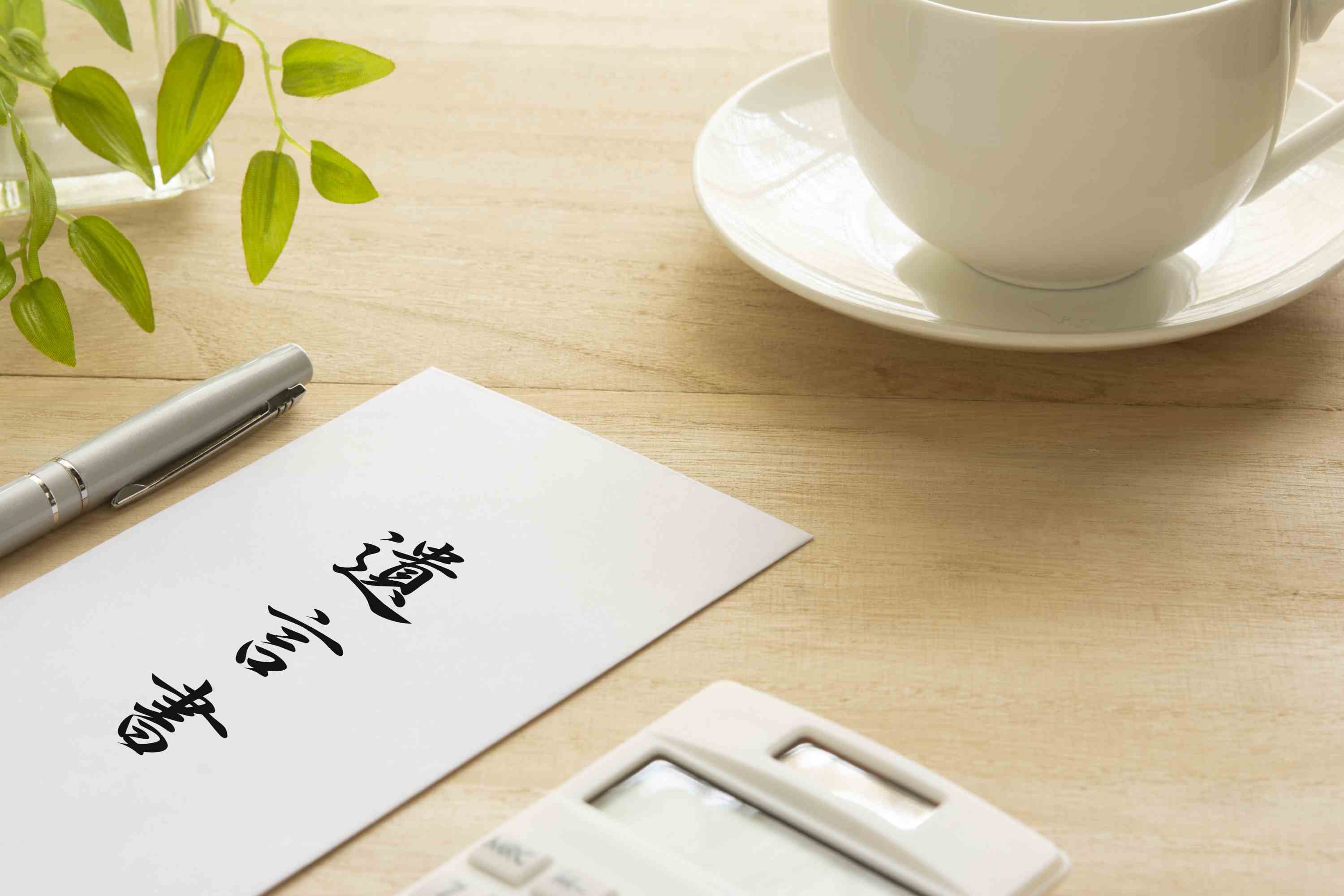
事実婚の嫁への遺産の残し方
2019-10-22
事実婚夫婦が直面する大きな問題の一つは遺産相続です。夫は老衰や不慮の事故にあった場合などを想定して、残された嫁ができるだけ生活に困らない様に、少しでも多くの遺産を残してあげたいでしょう。
しかし、夫婦間の遺産相続は法律上の配偶者かどうかを基準に行われるので、事実婚の夫婦はどんなに仲が良くても、遺産相続の場面では赤の他人になり、遺言書に遺贈(相続と似た意味合いです)する文言がなければ、原則として1円たりとも遺産を貰えません。
反対に、険悪な仮面夫婦や長年別居状態であったとしても、婚姻届けを提出している夫婦ならば、原則として配偶者である嫁が一番多く遺産を相続できます。
以上の通り、事実婚は遺産相続においては不利になることが多いのですが、法律で決まっているので致し方ありません。ならば、事実婚でもできる法律上での遺産の残し方を、詳しく紹介していきます。
遺産を貰える方法は主に2つ
遺言書
遺産相続においては他人である事実婚の妻は、原則として遺産を相続する権利はありません。遺言書で妻宛てに財産を遺贈する旨が記載されていて初めて貰う権利が出てきます。
夫に遺産を相続できる親族が居なければ、事実婚の嫁に全ての財産を遺贈すると書いておけば、問題なく財産を全て受け取れます。しかし、遺産を相続できる親族がいた場合は、その人も遺産を貰う権利があるため、全財産を受け取ることはできないことがあります。事実婚の嫁に全財産を遺贈する旨の記載があっても、一定の範囲の親族は、遺留分侵害額請求(以前は、遺留分減殺請求と呼ばれていました。)という制度により、ある程度の遺産を取得する権利があるからです。
遺産相続の割合は、話し合いで解決できれば一番良いのですが、難しいケースも多いため、弁護士に仲裁に入ってもらうか、それでも話がまとまらない場合は、裁判所の遺産分割調停を利用して話し合うのがいいでしょう。
遺言書は、自分1人で書いてもいいですが、法律に定められた形式で作成されていなければ無効になることがあります。。弁護士に相談したり、ネットで調べたひな形を参照したりして書きましょう。
公証役場では公証人という法律家の立会いのもと、間違いなく法律上効力がある公正証書遺言を作成することができますので、気になる方は作成をおすすめします。
そして、残された遺族がすぐに遺産を把握できるように、自分の資産を記載したエンディングノートや覚書などの書類があればスムーズに理解できて便利です。
特別縁故者
故人に相続人になれる身内がおらず、遺言書もない場合は、身の回りの世話をしていた人等が特別縁故者として、相続財産の一部または全部をもらうことができることもあります。財産を清算した後、相続人の不存在が確定してから家庭裁判所に申立てを行い、申立てが認められた場合に遺産を受け取れます。
認知した子供には相続権あり
事実婚のパートナーには原則として相続権はありませんが、二人の間にできた子供を認知していれば、その子供は実子であり、遺産を相続する権利があります。
事実婚のパートナーが相続すると全額が相続税の対象になりますが、実子であれば基礎控除が受けられます。
控除額の計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
子供が一人なら3600万円までの遺産相続が非課税になります。金額にもよりますが、子供に相続させた方が相続税の納税額は抑えられます。
生前贈与
年間110万円以下の贈与は贈与税の課税対象にはなりませんので、これを利用して複数年に渡り遺産を渡すのも一つの手段です。しかし、あまりに長期に渡って連続して贈与し続けると、税務署に合計額が一括で贈与されたものとみなされて課税の対象になる恐れもあります。
賃借物件は継続して住める
生前に夫婦がアパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいた。この時、通常の事実婚夫婦ならば、賃貸借契約に夫(未届)妻(未届)と二人の関係を記載しています。
この場合ならば、賃貸借契約の名義人である夫が死んでも、妻は賃借権を相続してそこに住むことができます。これは相続というより居住の継続に近く、家主と話し合えば、名義を自分に変更することもできます。
まとめ
法律婚の配偶者ならば、遺産を相続しても法定相続分と1億6千万円のうちいずれか多い方の金額までは相続税の課税対象にはなりません。しかし、事実婚のパートナーでは1000万円以下で10%の相続税がかかり、その課税の比率は金額に比例して増加。最大で6億円超で、税率は55%まで上がります。
贈与税も、110万円超から贈与額が増えるにつれて課税率は高まり、3,000万円超で税率は55%。相続税よりも比率の上りが早くて割高です。
法律婚と事実婚では税金の差は歴然です。ある程度の高額の資産がある人は、生前贈与だけではなく、法律婚(結婚)も視野に入れて見るのも一つの手段と言えるでしょう。
