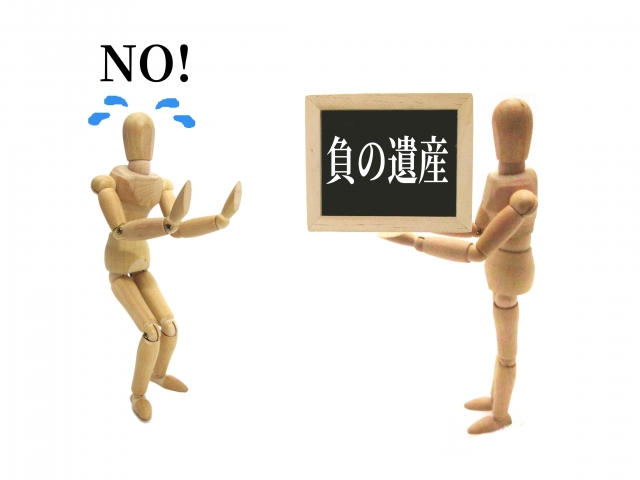
借金を相続しないために 相続放棄の手続きを解説
2019-12-01
相続は必ずしもメリットがあるとは限りません。被相続人(亡くなった方)に借金などのマイナスの財産があると、それも受け継いでしまうからです。
そんなときに有効なのが「相続放棄」です。被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、一切受け継がないというものです。ただし、相続放棄をするには所定の手続きが必要です。ここでは、その相続放棄の手続きについて解説します。
相続放棄は誰ができる?
相続人ができます。本人でも大丈夫ですし、弁護士に依頼することもできます。なお、「限定承認」という制度は相続人全員でしなければなりませんが、相続放棄は各相続人が単独でできます。
相続放棄はいつできるの?
相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内です。
例えば、行方知らずだった父親が3年前に亡くなっていたのが今日わかったという場合、亡くなってから3ヶ月以内ではなく、今日から3ヶ月以内です。
なお、3ヶ月を過ぎてしまうと、さかのぼって期間を延長することは原則的にできません。3ヶ月の期間内であれば、延長を申請することはできます。もし、迷っていて相続放棄の手続き期間が終わりそうならば、まずは期間延長を申請しましょう。
相続放棄は誰に対してするの?
相続放棄は家庭裁判所に対して行います。ただし、「被相続人の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所」です。つまり、亡くなった方の住民票がある場所の家庭裁判所です。
延長の申請をする場合も同様です。ちなみに家庭裁判所本庁は各都府県に1つずつ、北海道は4つなので全国に50カ所あり、支部・出張所を合わせると330ヵ所あります。もっとも、相続放棄の手続きをする場合、基本的には現地の家庭裁判所に出向く必要はなく、郵送で必要な書類を送るだけです。
相続放棄に必要な書類は?
相続放棄申述書
相続放棄の意思表示に必要な書類は、実は1つだけです。「相続放棄申述書」です。ただし、この後説明する添付書類が必要になるので、その点は注意してください。
「相続放棄申述書」というと難しそうですが、実は全国共通のフォーマットがあります。裁判所のホームページから記入例を含めダウンロードできます。
記入例をみてもわかりますが、ほぼ住所と名前を書くだけです。相続放棄の理由は○を付けて選ぶだけ。借金が多かったら「5 債務超過のため」に○を付けます。「相続財産の概略」の欄は、あくまで概略なので厳密な数字でなく、わかっている範囲で大丈夫です。相続放棄申述書に借金200万円と書いて出したものが後で1000万円だとわかっても、相続放棄が無効になることはありません。
添付する書類
「相続放棄申述書」には添付しなければならない書類があります。下記の通りです。
①被相続人(亡くなった方)の住民票除票(または戸籍附票)
②申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
なお、上記2点だけだと被相続人と申述人との関係がわかりません。そのため、資料として親族の場合は関係がわかる戸籍謄本なども必要になります。
相続放棄に必要な費用は?
相続放棄にかかる費用は、本人申請の場合は大した額ではありません。「相続放棄申述書」に貼る印紙代が800円。同封する切手代。あとは住民票除票や戸籍謄本を取るための費用だけです。
相続放棄での注意点
以下の行為をすると、期限内でも相続放棄ができなくなります。
①相続人が相続財産の全部、または一部を処分した
②相続財産の隠匿
特に①は注意が必要です。
なお、生命保険の受取人が相続人の場合、相続放棄しても受け取れます。祭祀財産も相続放棄しても引き継ぐことが可能です。また、いずれにせよ相続放棄してしまうと後で資産があったことがわかっても相続はできないので注意してください。
まとめ
高額の借金など、マイナスの遺産を相続してしまい、苦しむ事例はよくあります。相続放棄の手続きは驚くほど簡単で、通常はコストもかかりません。活用して悲劇を防いでもらいたいと思います。
