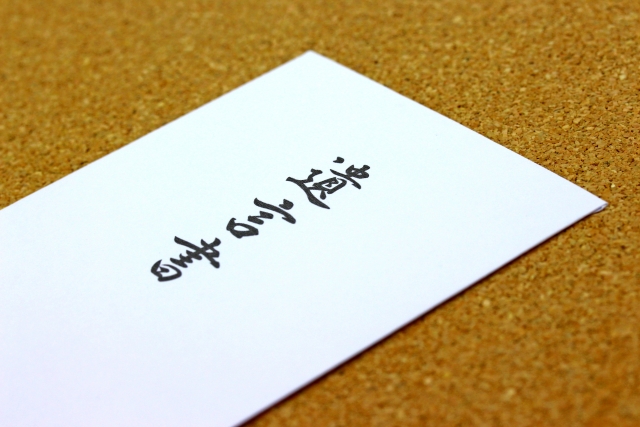
自筆証書遺言が無効になる6大ケース
2019-12-29
遺言は満15歳以上であれば作成可能です(民法第961条)。
しかし、年間の死者数はだいたい136万人なのに対し、公的に把握されている遺言者数は全体の1割に満たない程度に過ぎません。
ひとつには遺言の書き方がわからない点もあるでしょう。
ここでは、遺言が無効になる場合を通じて、効力のある遺言書の書き方について説明したいと思います。
遺言の種類
遺言には、次の4種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特別方式遺言
一般的に遺言書のイメージになるのは自筆証書遺言なので、今回はこちらを取り上げます。
なお、秘密証書遺言は、作成後に封印し、2人の証人と一緒に公証役場に遺言書を持参し、公証人、遺言者及び証人が署名押印するものです。自筆証書遺言と比べ、遺言書作成の記録が公証役場に残るメリットはあるのですが、内容に公証人が関与することはありません。
自筆証書遺言が無効(効力がない)になる6大ケース
ケース(1)遺言書を自書していない場合
これは、第968条第1項の規定(太字)によるものです。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
自書というのは自分で「書く」ことですから、パソコンで打つのはダメです。また、他人に書いてもらって、本人が「以上のとおり間違いありません」と書いたりしてもダメ。ここは厳しく全文書くものだと思ってください。
ただし、後述のように、財産目録はパソコンでも作成可能になりました。
ケース(2)そもそも書いていない
例えば、ビデオメッセージで遺言を残すなんてやりたいですよね。でも、これも自書に当たりません。もちろん、録音でメッセージを残してもダメ。とにかく、「文書で書く」これが自筆証書遺言の基本原則だと覚えてください。
ケース(3)日付がない
これは第968条第1項の規定(太字)によるものです。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
そもそもなぜ日付を書く必要があるかというと、2つ以上の遺言があった場合、最新のものが有効になるからです。どちらが最新かわからないと判断できません。
このため、特定の日として明確にする必要があります。普通に「2019年12月24日」という年月日の書き方がベストですが、「令和元年のクリスマスイブ」でも特定性は満たしているので有効になるかもしれません。
ただ、自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効だという判例(最判昭和54年5月31日)もあります。この場合も前後の状況から「吉日」がいつかわかるかもしれませんが、とにかく、危ないことはやめて年・月・日を正確に書きましょう。
なお、日付などを書いて署名捺印した瞬間に遺言書は完成します。その点では、本文を書いて、後に日付などを書き完成させることは可能ですが、これもトラブルを避ける上では、本文などを書いて、署名捺印もして日付を書いておくのが無難です。また、自書ですからスタンプではダメです。
ケース(4)署名がない
これは第968条第1項の規定(太字)によるものです。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
本文全文を自書するのですから、最後に署名するくらいは普通すると思いますが、全文を書いて安心してはいけないということですね。きちん署名を自書しましょう。自書ですからスタンプではダメです。
ケース(5)印がない
これは第968条第1項の規定(太字)によるものです。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
これは印鑑であればよいので実印である必要はありません。拇印でも認めた判例もあります(最判平元年2月16日)。ただ、裁判になったということは争いになったということです。基本的に実印が推せるのであれば、実印を押すのがベストです。
ケース(6)訂正が要式違反
これは第968条第3項の規定(下線部)によるものです。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない
要するに書き加えたり、削除したり、変更した場合は、それが明確になるようにして署名・捺印しないといけません。
例えば、「○○工業の株を」の「工業」を「電機」に直す場合、「○○工業」の「工業」に2重線を引き、その横に「電機」と書いて印鑑を押し、該当箇所の余白に「この行、2文字削除2文字加入山本晋三」のようにします。もちろん、これもすべて自書です。
なお、これは要式違反の場合、遺言書に効力がないわけではなく、訂正に効力がないということです(最判昭56年12月18日)。
3.効力のある遺言書とは
ケース(1)~(6)に当たらなければ、その内容が法律上、正しいかどうかは別として遺言書としての効力はあります。
なお、財産目録は上記の株式の例やあるいは土地の特定などで非常に間違いやすいため、2019年1月13日からパソコンで作成可能になりました。ただし、遺言本文との綴じ方などの注意が必要です。
まとめ
2020年7月10日からは、自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました。これは遺言書を法務局で保管してくれる制度です。法務省としても、遺言の活用を望んでいるということでしょう。自筆証書遺言であれば、基本的にお金は掛かりません。上記のポイントに注意して効力のある遺言書を書いてみてはいかがでしょう。
