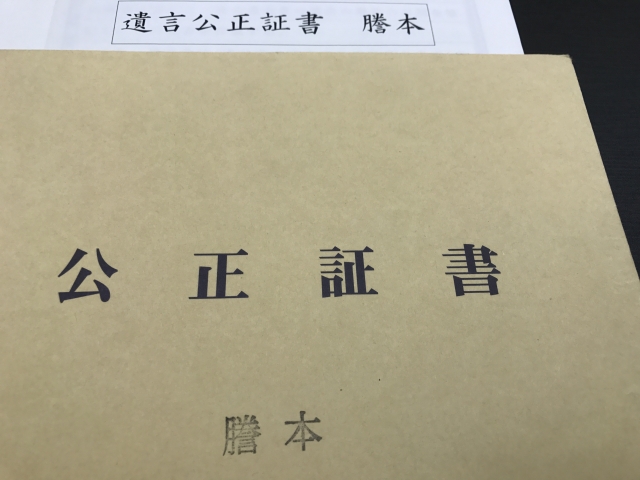
遺言の検認手続きってどうするの?
2020-01-22
テレビドラマではよく、遺言書を弁護士が遺族に開示するシーンがあります。かばんからおもむろに遺言書を取り出し、開封して遺族の前で読み上げる。でも、「それって検認が必要なんじゃない?」――そう、遺言書を開封するのには「検認手続き」が必要な場合があります。ここでは、遺言の検認がどんな場合に必要でどう進行するのかについて徹底解説します。
1.検認手続きが必要な場合とは?
一般的な遺言には3種類あります。以下の3種類です。
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・自筆証書遺言
このうち、検認手続きが必要なのは秘密証書遺言と自筆証書遺言の2種類です。
ここで、秘密証書遺言は作成時に必ず封をするのですが、自筆証書遺言では必ずしも遺言者が封をする必要がありません。つまり、遺族が自筆証書遺言を見つけた場合、簡単に中身を見ることができる場合があります。それでも検認は必要なのでしょうか?
答えはイエスです。遺言書が封をされているか否かに関わらず、公正証書遺言以外では遺言の検認が必要になります。検認は開封手続きではありません。この点、間違えないようにしましょう。
また、弁護士が遺言書を預かっていたとしても、公正証書遺言以外は検認が必要になります。弁護士が金庫に保管していた自筆証書遺言書原本を遺族の集まりに持って行って開封して中身を読み上げるということは、ドラマの中の話、実際にはあり得ません。
なお、封がしてある場合は、もちろんそのままにしておきます。
2.検認手続きを始めるには?
(1)検認の申立てができる人
検認手続きを始めるには、まず、検認の申立てが必要です。
この検認申立ては誰でもできるわけではありません。「遺言書の保管者」か「遺言書を発見した相続人」です。
例えば、遺言者から生前、遺言書を預かってくれと頼まれていた方がいた場合、相続人でなくても申立てができます。
相続人の場合、「発見した」というのは、厳密に発見でなくても構いません。遺言書を書いていたかどうかわからなかったけれど、家政婦さんが部屋を探してみたら遺言書があった場合、それを家政婦さんから受け取った相続人がいたら、それは発見したのと同じです。
(2)検認の申立先
例えば、遺言書を地元の市役所に持って行って検認できたら簡単なのですが、現実にはそうは行きません。まず、検認申立書を家庭裁判所に提出しなければなりません。しかも、申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所は各都道府県にありますが、多くの場合、都道府県内に支部があり、実際の申立先がその支部になるケースもあります。例えば、遺言者が亡くなった時の住所が、山口県下関市だった場合、山口家庭裁判所下関支部が管轄裁判所(申立先)になります。
申立先はあくまでも最後の住所地が基準 です。本籍や死亡地ではありません。たまたま旅行先で事故にあって亡くなったと言う場合、その死亡地の裁判所が申立先になるわけではありません。
管轄がわからない場合は、各都道府県の家庭裁判所に問い合わせをしましょう。裁判所のホームページを見ても管轄裁判所はわかります。
(3)検認申立書
検認申立書を書くこと自体は簡単です。
まず、「家事審判申立書」という書類ひな形の「事件名」の欄に「遺言書の検認」と記入します。
次に宛先の家庭裁判所名と申立日を記入します。
宛先の隣の申立人欄に記名押印します。例えば、複数の相続人が遺言書を発見した場合でも全員の名前を書く必要はなく、誰かひとりが申立人になります。
その次のページにも申立人欄がありますが、こちらは書類のデータとしての申立人欄と考えれば良いでしょう。もちろん、表書きの申立人と同じ氏名を記載します。表書きの申立人欄には印鑑を押しますが、後の申立人欄は住所と氏名と職業などを記載するだけです。相続人の場合は遺言者との続柄も問題になりますので、本籍も記載します。遺言書を預かっただけの相続人ではない者 の申立人は基本的に本籍を書く必要はありません。
遺言者は検認する遺言書を書かれた方になります。
「申立の趣旨」は、自筆証書遺言の場合は「遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求めます。」ですが、秘密証書遺言の場合は「遺言者の秘密証書による遺言書の検認を求めます。」になります。
「申立の理由」には、次の項目を必ず記載します。
・遺言書を持っている理由
・遺言者死亡の事実
・検認を求める旨
預かっていた場合は、いつ遺言者から預かり、どのように保管していたのかを記載します。例えば、「○年○月○日に遺言者から預かり申立人の自宅の金庫に保管していました」という感じです。
相続人が発見した場合は、例えば、「申立人が遺言者の自宅を探したところ、○年○月○日に書斎の机の引き出しの中で見つけました。封はされていませんでしたが封書の表に遺言書と書かれていました。」というように、誰が・いつ・どのようにして遺言書を発見し、それがどのような状態だったかを簡潔に記載します。
その他、遺言者がいつ亡くなったのかを明記するとともに、検認を求める旨を記載します。
また、別紙として、相続人全員の本籍・住所・氏名・生年月日・年齢を記載します。受遺者がわかっている場合は受遺者も記載します。
3.検認申立てに必要な添付書類等
(1)印紙と切手
検認手続き申立てには申立書の印紙添付欄に収入印紙800円分を貼ります。裁判所の手間を考えると800円はかなり安いと言えます。
また、裁判所は検認申立てがあったことを申立書記載の相続人全員に郵送で通知します。そのために切手も必要になりますが、こちらは申立先の家庭裁判所に問い合わせるのがよいでしょう。
(2)戸籍謄本
検認申立書 の作成はそれほど大変ではないのですが、相続人が遺言者の相続人であることを示すために、以下の書類などが必要になります。
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
場合によってはこれ以外の書類も必要になります。
4.検認期日まで及び検認期日での手続き
検認期日は申立てから数週間から1ヶ月程度になります。もし、遺言書に封がされている場合、中を見たいという誘惑に駆られますが頑張りましょう。
なお、開封しても遺言書が無効になったり、犯罪になるわけではありません。ただ、開封すれば、あとあとトラブルの原因になります。また、開封には行政罰が課されることがあります。
裁判所ではこの間、全相続人に通知し、遺言書の存在と検認期日を知らせます。申立人に問い合わせをすることもあります。
検認期日には申立人が出頭するのが原則ですが、代理人として弁護士に検認期日の出頭を頼むこともできます 。もちろん、遺言書も持って行きます。また、印鑑も必要です。その他の相続人は出席しなくても問題はありません。
裁判所では、裁判官が、遺言書の形状、内容、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の状態を確認します。
検認が終わると検認済証明書を発行してくれますので、その申請書も提出しましょう。
まとめ
遺言書の検認は遺言書が有効かどうかを判定するものではありませんが、遺言の執行には必須の手続きです。万が一、開封してしまっても検認は可能ですので、必ず検認手続きを踏むようにしましょう。
