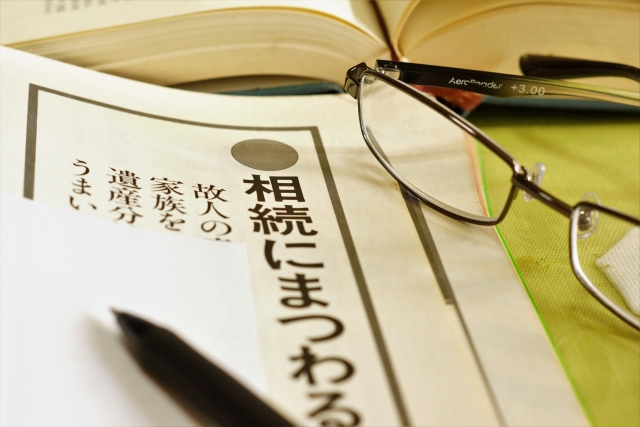
押さえておきたい!相続にまつわる書類~まとめ~
2020-01-28
相続に関する手続きには、多くの書類が必要になります。被相続人が亡くなって、その遺族が精神的に大変なときに、さまざまな書類を集めることは非常に困難なことです。しかし相続は、残された遺族(特に配偶者)の生活保障や、子孫繁栄のためには、とても大切な手続きです。
そこで、本記事では、相続にまつわる書面について説明します。
相続手続きに共通して必要となる書類
相続の手続きで代表的なものとして、預金口座の解約手続き、相続登記の手続き、相続税の確定申告の3つがあげられます。これらの手続きに共通して必要となる書類を紹介します。
被相続人の戸籍謄本
主な相続手続きとしては、預金口座の解約、不動産の相続登記、相続税の確定申告があげられますが、このすべてについて、被相続人の出生から死亡までの身分変動を明らかにする戸籍謄本が必要になります。
遺言書
被相続人が遺言書を残している場合には、相続手続きは遺言書にしたがって行なわれます。なお、遺言書が公正証書によって作成されていない場合には、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を受ける必要があります。遺言書があれば、遺産分割で相続人が揉めることが少ないので、手続きがスムーズに進みます。
遺産分割協議書
被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続手続きは、相続人全員による話合いにより作成される遺産分割協議書に従って行われます。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印する必要があります。遺産分割協議は全員一致が原則なので、協議内容に同意しない相続人が1人でもいると、手続きが進みません。
印鑑証明書
印鑑証明書は、相続手続きで遺産分割協議書を使う場合、その書面に添付します。原則は、相続人全員分が必要ですが、相続登記で遺産分割協議書を使用する場合、新たに登記名義人となる相続人の印鑑証明書は不要で、それ以外の相続人全員分が必要です。
相続人全員分の戸籍謄本
預金口座解約手続き、相続登記、相続税の確定申告で、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。相続人の戸籍謄本は、被相続人とは異なり、現在戸籍のみが必要となります。抄本でも構いません。
相続関係説明図
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係性を説明する図面のことです。この書面は、相続手続きに必ず必要だというわけではありませんが、作成しておくと、誰が相続人となるのかが一目瞭然となりますので、相続手続きがスムーズに進みます。
法定相続情報一覧図
相続関係説明図を、登記所の登記官が、戸籍謄本等によって確認し、間違いのないものであることを認証したものを「法定相続情報一覧図」といいます。この一覧図があれば、銀行の窓口や登記所、税務署で、戸籍謄本の束を提出しなくても、各種の相続手続きができるので、相続手続きが非常に簡単になります。
相続登記で必要になる書類
続いて、被相続人が残した土地や建物の相続登記に必要になる書類について解説します。
登記名義人となる相続人の住民票(写)
相続登記の申請書には、相続によって新たに登記名義人となる者の住民票(写)(マイナンバーの記載のないもの)を添付することが必要になります。
被相続人の住民票除票・戸籍の附票
相続登記の際に、登記簿上の被相続人の住所と現在の住所が異なっている場合には、被相続人の住民票の除票が必要になります。登記簿上の住所から現在の住所までに2回以上の転居がある場合には、住民票の除票の代わりに、戸籍の附票を添付します。
固定資産評価証明書
相続登記を行う際に、登録免許税が課税されますが、その登録免許税の支払額を算定する際に、固定資産税評価証明書が必要になります。さらに、当該証明書は、相続登記申請書の添付書類にもなります。
預金口座解約に必要になる書類
被相続人の預金口座を解約し、口座にある預金を払い戻す手続きに必要となる書類を以下で解説します。
被相続人の預金通帳
被相続人の預金口座を解約して、預金残高を払い戻す手続きを行う際には、被相続人の通帳が必要になります。死亡時点で慌てないように、生前に、預金通帳などを一か所にまとめておくとよいでしょう。
相続税の確定申告に必要となる書類
相続税の確定申告に必要となる書面は、ケーズバイケースで、しかも、非常に複雑です。従って、極めてシンプルな相続は別として、一般的には、税金の専門家である税理士に確認するのが良い方法です。
まとめ
相続手続きには非常にたくさんの書類が必要になり、それらを集めるには多くの苦労が伴います。しかし、最近では、法定相続情報証明制度という便利なサービスが利用できるようになっていますので、これを効率的に活用して、できるだけスムーズにこの手続きを行ないたいものです。
