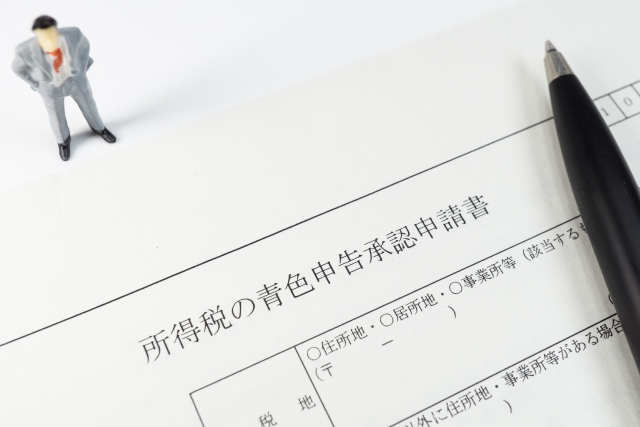
故人の事業を相続するときの手続き~所得税の青色申告承認申請書~
2019-11-23
記帳の手間は増えるものの、受けることのできる恩恵も大きい青色申告制度。
不動産を相続した場合などの相続税については関心がある方が多いものの、所得税に関わる承認申請書についてはうっかり提出を忘れてしまうこともあるようです。
今回は、故人から事業を相続した場合の青色申告承認申請書について解説します。
青色申告承認申請書とは
事業所得、不動産所得、山林所得のうちの1つ以上を有する場合に青色申告を行うと、帳簿を正確に付けることの見返りとして、所得から65万円の特別控除を受けることができます。
そのために税務署へ提出するのが「青色申告承認申請書」と呼ばれるもので、青色申告者として承認されると、それ以降は本人が青色申告の取りやめる旨の書類を提出した場合を除いて基本的にその効力は持続します。
申請書を提出する際は、納税地として住所登録している地域を管轄する税務署長に提出してください。
提出期限は以下のように定められています。
・法人の場合
原則:事業年度を開始した日の前日までに提出
例外:新規設立の場合は、事業年度を開始した日から3か月以内に提出。(3か月以内に事業年度が終了する場合は、事業年度終了の日までが期限となります)
・個人の場合
原則:青色申告を行う年の3月15日までに提出
例外:青色申告を行う年の1月16日以降に新規で事業を開始する場合は、開始日から2か月以内に提出
相続時の青色申告承認申請書に提出について
故人から事業を相続した場合も上記と同様に、青色申告承認申請書を税務署へ提出することになります。
ただし、このケースでの青色申告承認申請書の提出期限は、被相続人が生前に白色申告と青色申告のどちらを行っていたのかによって異なってきます。
そこで、ここからは被相続人の申告方法について、ケース別に解説します。
※相続人が別の事業で申告を行っていないことを前提とします。(相続人が相続する時点で別の事業で申告をしている場合は、被相続人の生前の申告方法にかかわらず通常時と同様の取り扱いとなるため)
故人が青色申告で申告していた場合
青色申告を行っていた故人から事業を相続した場合は、相続が発生した日(被相続人が死亡した日)に応じて、下記の期間内に管轄の税務署長に申請書類を提出してください。
提出期限が土日や祝日等となる場合は、その翌日が提出期限となります。
・1月~8月末の間で相続が発生した場合は、相続が発生した日から4か月以内(準確定申告の期限とほぼ同じ)
・9月~10月末の間で相続が発生した場合は、その年の12月31日まで(準確定申告期限より短い)
・11月以降に相続が発生した場合は、翌年2月15日まで(準確定申告期限より短い)
故人が白色申告で申告していた場合
白色申告を行っていた故人から事業を相続した場合は、相続が発生した日(被相続人が死亡した日)から、以下のいずれかのうち遅い方の期日までに管轄の税務署長に申請書類を提出してください。
・1月15日までに相続が発生した場合は、3月15日まで
・1月16日以降に相続が発生した場合は、その日から2カ月以内
青色申告を行っていた場合に比べて期間が短いため、うっかり申告漏れとならないよう注意が必要となります。
申請書の記入内容
下記について申請書に記載が必要となります。
・所轄の税務署の名前
・書類の提出日
・事務所の屋号と住所
・申告を始める年
・納税地の住所、電話番号
・職業(業種など)、屋号(ない場合は空欄でもよい)
・所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得)
・青色申告承認の取り消しもしくは取りやめの経験の有無
・相続による事業承継の有無(「有」をマークして、相続開始年月日と被相続人の氏名を記入)
・簿記方式(複式簿記、簡易簿記など)
・備付帳簿名(備え付ける帳簿名を選択する)
65万円の控除をしっかりと受けるためにも、簿記方式は必ず「複式簿記』を選択し、備付帳簿名は下記の8つを選択しましょう。
現金出納帳:出入金の状況を取引順に記載
売掛帳:売掛金の回収状況を記載
買掛帳:買掛金の支払い状況を記載
経費帳:仕入れ以外の必要経費を科目別に記載
固定資産台帳:減価償却資産などの取得及び異動に関する事項を記載
預金出納帳:口座毎の入出金を記載
総勘定元帳:勘定科目に基づき全取引を記載
仕訳帳:日付順に全取引を記載
まとめ
青色申告によるメリット(所得税の大幅な圧縮、住民税の削減など)は数多くあります。手続きが漏れてしまって、せっかくのメリットが享受できない…なんてことの起きないようにしたいものです。
